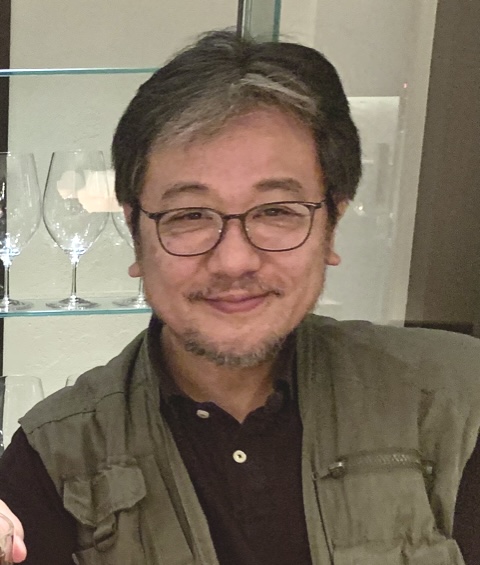不機嫌なアランの遺したもの–正常性バイアスという陥穽
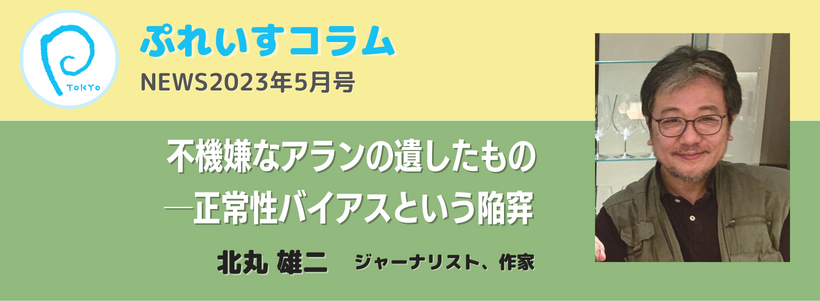 ニューヨークの病院に、アランというゲイの青年がエイズで入院しているから自分の代わりに見舞いに行ってくれないかとカナダの友人に頼まれて、私は指示どおり赤い薔薇の花束を買ってコロンバス・サークル西側にあった病院のエイズ階に彼を見舞いました。今から30年前の1993年5月、同地に赴任して3ヵ月後のことでした。
ニューヨークの病院に、アランというゲイの青年がエイズで入院しているから自分の代わりに見舞いに行ってくれないかとカナダの友人に頼まれて、私は指示どおり赤い薔薇の花束を買ってコロンバス・サークル西側にあった病院のエイズ階に彼を見舞いました。今から30年前の1993年5月、同地に赴任して3ヵ月後のことでした。
がらんとした広い個室でひとりベッドに横になっていたアランは、私を見るなり初対面の挨拶もそこそこに、下痢がひどくて動けないと言って尿瓶の処理を命じてきました。私は個室のトイレにそれを流し、洗い、持ってきた薔薇を花瓶に挿して病床の横に飾りました。ただの使い走りだった私に話すべきことはなく、問うべきことは不躾に過ぎるやも知れず、病いに疲れる彼にも見ず知らずのアジア人相手に打ち明けるべき身の上話はありませんでした。エイズ発症者に不慣れな私との差し障りのない言葉のやり取りの中で、まだ30歳ほどだったのだろう彼は明らかに不機嫌で無愛想でした。居心地の良くない数分間か十数分間をやり過ごしてから、私は曖昧な作り笑いとともに別れを告げて病室を後にしました。いま思えば、その宙ぶらりんの笑顔は彼にはどう映ったのだったか──。
おそらくエイズに対する日本とアメリカとの彼我の差は、その時の意味不明の私の微笑みと、明示的だった彼の不機嫌の差だったのだろうと、今の私にはわかります。エイズを「死病」から解放する契機となったカクテル療法が一般化するまで、まだ3年ほどが必要でした。それ以前に十数年にわたって、アメリカのPWH/Aとその組織やアライたちは世界の最前線でこのウイルスとそれを放置する社会を相手に、それこそ「死闘」を繰り広げていたのです。
*
日本人がしばしば無意味に、あるいは無闇に「微笑」んでいる事実に気づかされたのは、実はアメリカ社会を身をもって知ってからでした。たとえばよもやま話でも恋愛相談でも人生相談でも、あるいは事件事故の目撃談の際も、相手の前あるいはマイクの前で私たちはほぼ習慣のように微笑みを浮かべ、時には自分の言ったことを必ず笑い声で締めくくる人もいます。まるで時代劇の悪代官のように。そんな時に「なにか可笑しい?」とアメリカ人に訝られあるいはほぼ咎められて初めて、私たちは私たちの「笑い」が「可笑しいこと」と結びついているというよりもむしろ、深刻な事実を重々しくしないための緩衝材、傷つかないあるいは傷つけないためのぼやかしの潤滑剤効果を持つのだと(これまた笑いながら)言い訳をしなければならない事態に陥っていることに気づくのです。
深刻な事実、予期せぬ事態を微笑みで曖昧にすることは、それを認知する心の過剰な疲弊を避けるための、必要なメカニズムではあります。しかしそれを日常的に続けているとそれ自体が認知のクセとなり、本当に深刻な被害が予想される事態になっても十分な対応ができないことあるいは遅れることにつながります。実際の津波の凶悪さを知るまでは「ここまでは来ない」「大丈夫だ」と思って逃げ遅れてしまうこの認知の歪み、深刻な情報のなんとはなしの否認を、社会心理学では「正常性バイアス」と言います。
*
一方で人類は、大きな悲劇を社会が共有したときに、その社会が次なる悲劇を回避する新たな次元に進化する営みを重ねることで生き延びてきました。世界大戦然り、チョルノービリ然り……けれど東日本大震災の東電福島第一の事故で、「次なる悲劇の回避」に動いたのは当の日本ではなく脱原発を成就させたドイツでした。日本は逆に原発稼働可能年数を60年に引き延ばした……。
「大きな悲劇」を社会が共有するためには、まずは悲劇を悲劇と認知すること、深刻な状況を否認しないことが大前提です。その上で初めて「反・悲劇」たるその社会の理想と未来とを構築し得る。
しかし「正常性バイアス」が癖になっている社会では、常に薄笑いを浮かべたまま「大きな悲劇」をいつまでも認知できない。未来は悲劇の火種をブスブスと烟らせたまま、そこに蓋をして続いていくのです。「なんか焦げ臭いけど、ま、大丈夫か」と。
エイズも同じでした。
日本のエイズ禍の規模は多くの国とは比較にならないほど小さかった。東アジアの島国という地理的な要因と心理的な人種鎖国のおかげです。そしてそれが結果としてエイズという、この時代の「大きな悲劇の共有」を妨げた。
一方でエイズ禍で最大の、そして最前線の国アメリカは1980年代をレーガン政権のエイズ放置政策で悲劇拡大に費やします。しかしこれを社会的かつ文化的な「大きな悲劇」の共有に繋げる努力がPWH/A当事者たちばかりか報道、音楽、放送、映画、スポーツ、教育、司法、企業などをも総動員で巻き込んで展開する。
この「悲劇」への反攻が1985年の戯曲『ノーマル・ハート』やNBCのドラマ『An Early Frost』(『早霜』の邦題でNHKが1989年に放送)、1991年からの『エンジェルズ・イン・アメリカ』などのエイズ関連の名作をも産み大衆レベルに浸透してゆくのですが、重要なのはそれが同時に、男性同性愛者たちを主とした人権運動への支援とそれに伴う「アイデンティティの政治」の確立、性的少数者たちへの「政治的正しさ」の適用にも徐々にかつ大規模に広がっていったということでした。それがひいては、不機嫌なあのアランを含む数々のマイノリティに対する、ひたすらに真面目な社会の受容・包摂へと大きく進むのです。
*
対して同じころの日本は「大きな悲劇」を認知していませんでした。規模こそ違えど、エイズは、では、「大きな悲劇」ではなかったのか?
そんなことはありませんでした。日本でも同じように性的少数者への揶揄と侮蔑と差別とが蔓延し、エイズ死は社会的問題としてではなく個人的責任の死、自業自得の死、汚辱に塗れた死として名前も知られることなくあるいは名前を知られることを恥じたまま死んでゆかざるを得ない人々が多く存在した。その悲劇は、正常性バイアスに伴うあの「微笑」ではなく「嘲笑」とともに「異常性」のカテゴリーに強制収容され、日本という正常社会の中には存在しないものとして「小さく、無関係な悲劇」の中に隔離されたのです。
日本でエイズ・ドラマとして大きな賞賛を浴びた(そしてほぼ唯一のドラマだった)フジTVの『神様、もう少しだけ』が放送されたのは、とうにカクテル療法の始まっていた1998年7月であり、HIVに感染するのは痛々しくかわいそうな女子高生でした。存在していたはずの「大きな悲劇」は、その本質に触れることなく世間受けするフィクションの、手慣れた悲劇に置き換えられていたのです。
こうして私たちは今に至るまで深刻な現実と向き合う機会を逸したまま微笑みながら頷き合い、大きな悲劇にひたむきに対処する方法を忘れてしまったかのようです。激甚化する気候変動も沈降したままの経済も産業構造の無変革も、社会変化を認知しない婚姻の不平等も強制的夫婦同姓も、統一教会に解散命令を出せないことも口出し手出しの日本会議や神社本庁にも、「大したことではない」「今でなくとも大丈夫だ」という正常化バイアスのもとで固く目を瞑ったあるいは瞑らさせた、現実世界と致命的に乖離した股裂き状態の政治が続いています。後ろに落とされたハンカチを拾うことはそっちのけでやれ大阪IRだ、やれ札幌五輪だ、やれ対中対北防衛費だと浮かれるだけの国は、これから一体どこへ行こうとしているのでしょうか。悲劇のドッヂボールは、いかにボール躱しの上手い選手がいても、彼ら彼女らだけでは負けます。
*
不機嫌なアランは私の見舞いの数カ月後に亡くなりました。彼とエイズ禍のアメリカ社会が私に教えたものは、理不尽な世界にはときに笑わない不機嫌と無愛想を貫くべきだという生き方でした。向かってくるボールを胸で受け、投げ返す選手がいなければ悲劇のドッヂボールには勝てないという勇気でした。
『ぷれいす東京NEWS』のご案内
ぷれいす東京では、普段の活動のなかで得た多様でリアルな声(VOICE)を『ぷれいす東京NEWS』にて発信しています。
- 外部のメール配信システム(ブレインメール)よりお届けします。
- 登録/配信解除/アドレス変更の手続きは、専用ページから設定をお願いします。
- ブレインメール(e.bme.jp)と、ぷれいす東京(ptokyo.org)から、受信できるようにしてください。
- 年4回配信予定。次号から自動配信になります。
過去のニュースレターは、こちらからご覧いただけます。